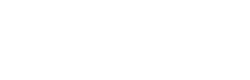安齋 新・厚子
繊細な静けさとのびやかさ、凛とした緊張感がありながらもやわらかなフォルム。
古道具のような懐かしさを持ちつつ、モダンさも感じる安齋新さん・厚子さんの作品。
相反する要素が共存するバランス感は、ひとつの器をご夫婦で作り上げることから生まれるのかもしれません。
天然の釉薬から生まれる、湖に映る森のようにつややかで静かな色合いも心に響きます。
様々な料理を受け止め、お手持ちの色々な器との相性もよく、懐が深い器です。
古い良いものを見れば見る程、モノを作る事はつくづく難しいと思う
思いも寄らずに納得のいくものが出来たとしたも、さらに奥を追求し苦しくなる
やきものって難しい
だけど楽しくもある
自分が好きだなと思うものを人と共有できた時が嬉しく
そんな出会いがあることを楽しみに
どなたかの食卓が豊かになればいいなと、今日も土に向かう
安齋 新・厚子
安齋 新 プロフィール
- 1971
-
広告カメラマンの父と絵本作家の母のもとに、次男として東京の郊外で生を受ける
- 1974
-
リトミックなどの教育方法を取り入れている幼稚園に通う
砂場が好きで、授業参観中ですら抜け出し泥遊び三昧だったと後年云われ続ける - 1977
-
小学校に上がっても砂場遊び好きはしばらく続く
図工の時間に紙粘土をニスで塗って恐竜みたいな物を作った時、東京都の何かに選ばれて嬉しかった
- 1979
-
毎年お盆の時期に母親の郷里である山形県の城下町・鶴岡に行き、従兄弟達と海に山にお祭りに行っていた
大正ガラス戸の廊下を渡って蔵へよく足を運んだ
古臭い匂いが充満している薄日だけの蔵の中は怖かったが、探検してお宝を発見するの自分だけのもう一つの楽しみだった
いま振り返ると、東京の住宅街には無い日本の原風景の一つだったのだなと思う - 1980
-
喜太郎のシンセサイザーのテーマ曲が印象的な『シルクロード』というNHKのドキュメンタリーに嵌る
西域と呼ばれる乾ききった風土がとてもエキゾチックで、いつか行って見たいと思ったりしていた - 1981
-
兄に倣って進学塾に行くも、兄とは違い箸にも棒にも掛からず直ぐにドロップアウト
その頃から「自分とは何か」とモヤモヤし始める - 1988
-
高校卒業が見えてきた頃、親の知り合いの陶芸家の家に遊びに行く
山深い仕事場に行ってみると薪窯の素焼きを焚く日で、夜通しの重労働を体験する事に
窯炊きが終わった安堵感と、あたかも一人前になったかの様な達成感が気持ち良かった - 1989
-
卒業間近になり大慌てで美術系の大学を受験するも、準備不足で不合格
一般大の文学部に入学する - 1992
-
どこかモヤモヤ続きで色々な物を見たくなり、大学を一年間休学
仕事を紹介してもらいながら北米、ヨーロッパ、イスラエルなどを旅する
イスラエルの美術館などでローマ時代のタイルやガラスなどの工芸品に改めて魅了され、自分も何かこういった物が作れないかと考える - 1993
- 帰国後はバイトの傍ら日本の風物なども見たくなって「そうだ京都に行こう」と思い、行ってみたりした
- 1994
-
法政大学文学部卒業
縁があって、益子にある加茂田窯に三ヶ月ほどお世話になる
ロクロや釉薬などの陶磁器のイロハと思える事を習いたいと思うようになる - 1995
-
有田窯業大学校に入学
ロクロや釉薬も面白かったが、石膏での成形も好きだった
ブランクーシなどの彫刻が好きだったからか、塊を削ったり磨いたりする原型を作る作業工程に特に惹かれる
石とは異なり土は焼くと痩せていくようで、思ったように表現出来ずなかなか難しかったが、様々な事を学び充実した日々だった
京都の陶芸家、寄神宗美さんのところで厚子と出会う
当時は、今のようになるとは思ってもいなかった - 1998
-
卒業後、実家の近くに友人と共同で窯を築く
なかなか思うようなものは作れず苦労する - 2000
-
共同窯の友人がウラバートルの大学で焼き物を教えに行くこととなる
苦しい時に何とか凌げたことに、今でも友人に感謝している - 2001
-
企画展に多数参加
少しずつ制作が見えてきて、手狭になったこともあり引っ越しを考える - 2006
- 石川県加賀市大聖寺という小さな城下町の町家に移住、結婚
- 2008
- 展示会の企画でオカズデザインと出会う
- 2013
- 長女が生まれる
- 2014
- カモシカで初個展「お粥さん」を開催
- 2018
- カモシカで二回目の展示「翠」を開催
- 2020
- コロナ禍中に、京都の北部にある京北に移住。林業が盛んな山深い町
- 2021
- カモシカで三回目の展示「冬じたく」を開催
- 2024
-
カモシカで四回目の展示「芽吹く」を開催予定
現在に至る
安齋 厚子 プロフィール
- 1974
-
京都市に生まれる
両親が共働きだった為、日中は明治生まれの母方の祖母に育てられ、おばあちゃん子として育つ
祖母は梅干しを漬けたり炭火で塩昆布を焚いたり、孫の誕生日など何かの時には必ずちらし寿司を作ってくれた
お正月の銘々の椀、季節のうつわ、この料理にはこのうつわと何となくいつも決まっていて、その繰り返しが子供心にも落ち着き、ささやかだが豊かな食卓の風景をよく覚えている - 1977
-
家は市電の駅前で町中だったが、幼稚園は東福寺近くの山中に有り緑豊かだった
毎月21日に開かれる東寺の弘法さんの日はお休みになる?仏教系の幼稚園
近くの粘土山を駆け登り、自然の中で毎日のびのびと遊ぶ - 1981
-
手仕事に興味が有り、絵や字をよく描いていた
買い物に着いて行くとお店の人の手の動きを見るのが好きだった
取り分け好きだったのがお漬物屋さんで、薄暗い店内で樽からお漬物を取って袋に入れる無駄のない手の所作を興味深く見入っていた
家中のハンカチを水に浸け、ビニール袋でハンカチを掴み、片手でクルッと返して入れるお漬物屋さんごっこは定番遊びだった - 1992
-
将来は手を動かし何かを作る仕事がしたいと漠然と思い、建築やインテリアの道を志す
- 1996
-
自分の手で最初から最後まで完成させるもの作りがしたいと思い、大学受験で一度意識した陶芸の道に進むことを決意
今となっては、うつわも使い手との共同・共鳴作業で完成するので、作って完成では無いと感じている - 1997
-
走泥社の寄神宗美氏に師事
土や釉のテクスチャーに惹かれ、生の土が乾燥していく変化だけでも楽しかった
この頃、安齋新と出会う - 1998
-
美濃国際陶芸展 金子潤審査員特別賞
- 2000
-
やきものを含め広い世界が見てみたくなり、知り合いを頼りに一年間アメリカを西から東へ
当時活躍されていた、アメリカ現代陶芸のトシコタカエズ氏、ピーターヴォーコス氏、金子潤氏などに会う
そんな中で見た浜田庄司さんの展示会でオブジェでは無く、ひとつの碗や一枚のお皿など、日常のうつわの美しさ、佇まい、存在感に衝撃を受ける
日本に戻り一からうつわ作りを勉強したいと強く思い、数ヶ月後に帰国 - 2001
-
京都市工業試験場専修科で、主に轆轤と釉薬について学ぶ
- 2003
-
独立、東京の安齋の窯を借り制作を始める
と言っても仕事は無かったので、半年後に展示会を入れ、アルバイトをしながら展示会に向けて作る日々
東京の仕事場が手狭になったことと原料などが手に入りにくい理由から、別の場所を探すもなかなか見つからず、ようやく石川県加賀市大聖寺に落ち着く - 2006
-
石川県加賀市に移住、結婚
安齋と衣食住を共にするうちに、自然と一緒にうつわ作りを始める
一人で活動していた頃は、ひとつひとつが作品という考えが強くがあったが、二人で作ることで、良い意味で使うことを先に考えるようになり、うつわとして表現の幅も広がっていった
自分の手跡や気配は消しても消してもうつわに残っているもので、料理を盛ることで完成するには、そのくらいの加減がいいなと感じるようになる
薄日が差す築100年の蔵での生活、日本海の海の幸が美味しい城下町での暮らしは、うつわを作る上で刺激を受けた - 2008
- 展示会の企画で料理担当だったオカズデザインと出会う
- 2013
- 長女出産
- 2006
-
カモシカで初個展「お粥さん」を開催
DM写真は、今回も制作した粥碗に梅干しとお粥さん
普段の展示会とはまた違った料理とのコラボレーションをこれ以降も毎回楽しむ
- 2018
-
カモシカで2度目の展示会、蒜山耕藝との夫婦二組四人展「翠」を開催
DMは青磁菱形菊鉢に水餃子
- 2020
-
京都の山中、京北に移住
広々とした空の下、山に囲まれた暮らしは、北陸とはまた違う光と匂いがする(時に獣臭)
海の幸は手に入りにくくなったものの、より自然と近くなり、採れたての野菜と少々不便な暮らしからまた暮らしに纏わるものを作って行きたい - 2021
-
カモシカで三回目の展示「冬じたく」開催
自分達がイメージする洋食器を中心に制作
- 2024
-
カモシカで四回目の展示「芽吹く」を開催予定
現在に至る