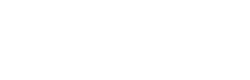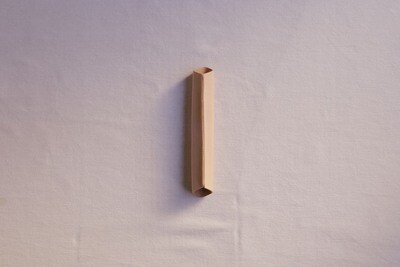PECHKA(ANDADURA)
PECHKAは感覚に寄り添う道具を作っています
ペチカは家を暖める大きな暖炉です
人々が集う食卓であり、病を癒し体を健やかに整える寝床でもあります
生活の中の祈りの場として、人々の誕生から死の傍にペチカはありました
感覚をつかうその先に、あるいは、その中にある祈り
その静けさにPECHKAの道具が寄り添えたらと思います
ANDADURA 山本祐介 / OKAZ DESIGN 吉岡秀治・知子
ANDADURA プロフィール
- 1982
- 生まれる。左利き、B型、3人兄弟の真ん中
- 1985
-
さまざまなものを分解するのが好きだったよう。父曰く、ビデオデッキにトーストを入れたりしていたらしい
大げさに言えば、ものの構造への興味はこの頃から。三つ子の魂百まで。犠牲になったものたちに、ありがとうと伝えたい - 1990
- 片道約5キロの道のりをバスと競争しながら走って通学。からだを動かす日々。まむしに噛まれていないのが不思議なくらいの野生児的生活
- 1991
-
学校に行かなくなる。一人の楽しさを知る
ローマ字は母が買ってきたローマ字絵本『RASYOUMON(羅生門)』で覚えた
折り紙にもはまり、公園で折り紙を教えたりもしていた。翌年復学 - 1995
-
書類を入れる鞄が見当たらないという祖母に、着ていたトレーナーで即席ショルダーバッグをつくる。後日お礼にミシンをもらう。この時から今に至るまで、ミシンと共に生活するようになる
初代ミシンはシンガーのコンピューターミシン。直線縫いしか使わなかった - 1996
- テレビで見たファッションショーにビックリし、服飾の世界に行こうと思う。広島の大きな手芸店マキに通いはじめる
- 1997
-
服飾の世界に行くので、勉強はしなくてもいいやと思い込み、美術の授業をたくさん受けられる自由選択制の高校に入学。案の定、まったく勉強をしなくなる
その代わりに、授業中は読書、家に帰ってからは映画の世界にどっぷり浸かる
デッサンの授業、ものを観察することで、自分がいかにイメージで世界を見ていたかに気づく。絵を描くことそのものよりも、絵を描くことでものの見方が変わっていく自分自身の変化が面白かった - 1998
-
卒業出来る程度に学校に通いつつも、美術館や好きな場所をフラフラして過ごす。いつでも好きな場所に行けるよう、カバンには常に私服を入れていた
手芸店マキで手に入る材料に限界を感じはじめる。この頃は、1つ作るのにミシン針を5本くらい折りながらの分厚い生地で制作。刺繍が得意な友人に刺繍を依頼したりもしていた - 1999
-
バウハウス展を美術館で観て衝撃を受ける
学校をさぼって2日続けて見に行き、デザインの方向へ行くことにする - 2000
-
大学生になり大阪に住む。入学したのは、スペースデザインコース。スペース=全てのものをバウハウス的にデザインする学科だと勘違いしていたことに気がつく
この頃よくリュックを作っていた。広島よりは手に入る材料が少し広がったが、手芸店で手に入る素材に限界を感じていた。ソファーの張り替えも好きで行う
実家に帰郷した際、高校生の頃に遊びで作った、忍者タートルズの亀の甲羅を模して作ったタートルズバッグを母が普段使いしていた - 2004
-
春 店舗設計会社で働きはじめ名古屋に住む。住む場所選びは大きな手芸店が近くにあること
週末に靴作りの学校に通う。その頃に作った靴は、父が今でも履いているそう
冬 店舗改装の際、廃棄トラックを早朝に見送る。数ヶ月前に作ったばかりのものがゴミになって荷台に乗っていた。徹夜明けのぼんやりとした頭でも「こんなことはしたくない」とはっきりと思った - 2005
-
春 会社をやめる。たまたま近所に大きな図書館があったので、毎日図書館に通って過ごす図書館生活をはじめる
朝から晩まで、ごりごりと本を読む。社会の中で自分をどう活かすのか、切実な思いでページをめくる日々。白髪がすごく増えた
秋 図書館に通うことしかしていなかったので、お金が尽きてくる。その頃に出会った養老孟司さんの「体はシステムから自由だ。」という言葉で肉体労働をしようと思い立つ
自分が楽しめる肉体労働は何かと考え、ミシンを踏むことだなと思い至る。本格的に学ぼうと東京のカバンの学校に通うことにする - 2006
-
「肉体労働をしに東京に行く」というイメージにワクワクしながら上京
カバンの学校に通うも、これでは作れるようにならないと感じ、4回でやめる。実際に働いてみようと思い、カバン工房で働きはじめる
カバンから小物の制作。営業や、修理・特注対応など、さまざまなことをさせてもらう - 2008
- 都心から離れた場所に友人とルームシェアをし、なんとか自分の工房を持つ
- 2010
-
ANDADURAをはじめる。その頃読んでいた、細野晴臣さんの本に「ANDADURA」の文字を見つける。歩くという意味は、散歩が好きな自分にはピッタリだと思う
歩くことで 素になっていく
歩くことで 浮かび上がってくるモノがある
歩くことで 形を成していく私がいる
という、逍遥学派の詩のような、歩くようなものづくりがしたいと思う - 2011
-
益子に移住。「体はシステムから自由だ。」という言葉に出会ってから、身体を通し感じ、考えるという「身体性」が自分の中で大きなテーマとなり、昔の人のような暮らしがしたいと思う
益子への移住はスターネットの存在も大きかった
洗剤が凍るようなボロボロの家で「家電のある原始人の暮らし」をはじめる。春の到来がすごくうれしかった - 2016
-
岡山に工房を移転する。大きなガレージの中にテントで部屋を作って工房にする
西日本豪雨で工房が浸かり、移転。現在の工房を友人に協力してもらいながら作る。人と共に作る楽しさを味わう - 2022
-
カモシカで初個展「ペチカ」開催
-
今、こうやっ振り返ってみると、常にミシンとともに過ごしてきたみたいです。おばあちゃんありがとう。
最近、バウハウス展で手渡されたものは「デザイン」というジャンルではなく、バウハウスの総合的な目線、ものを作るときの人への眼差しのようなものだったのだと、思い至りました。
もの、ひと、生活にそそがれる眼差しに感応したのだと。
自分がそこで感じた眼差しで世界を眺めることが出来たら「何を作ってもいい」と思うようになり、肩の力が抜けました。
これから自宅の改装を始めます。自分の暮らしに向き合うことで、何かが生まれてくるのであろう予感とともに日々を過ごしています。